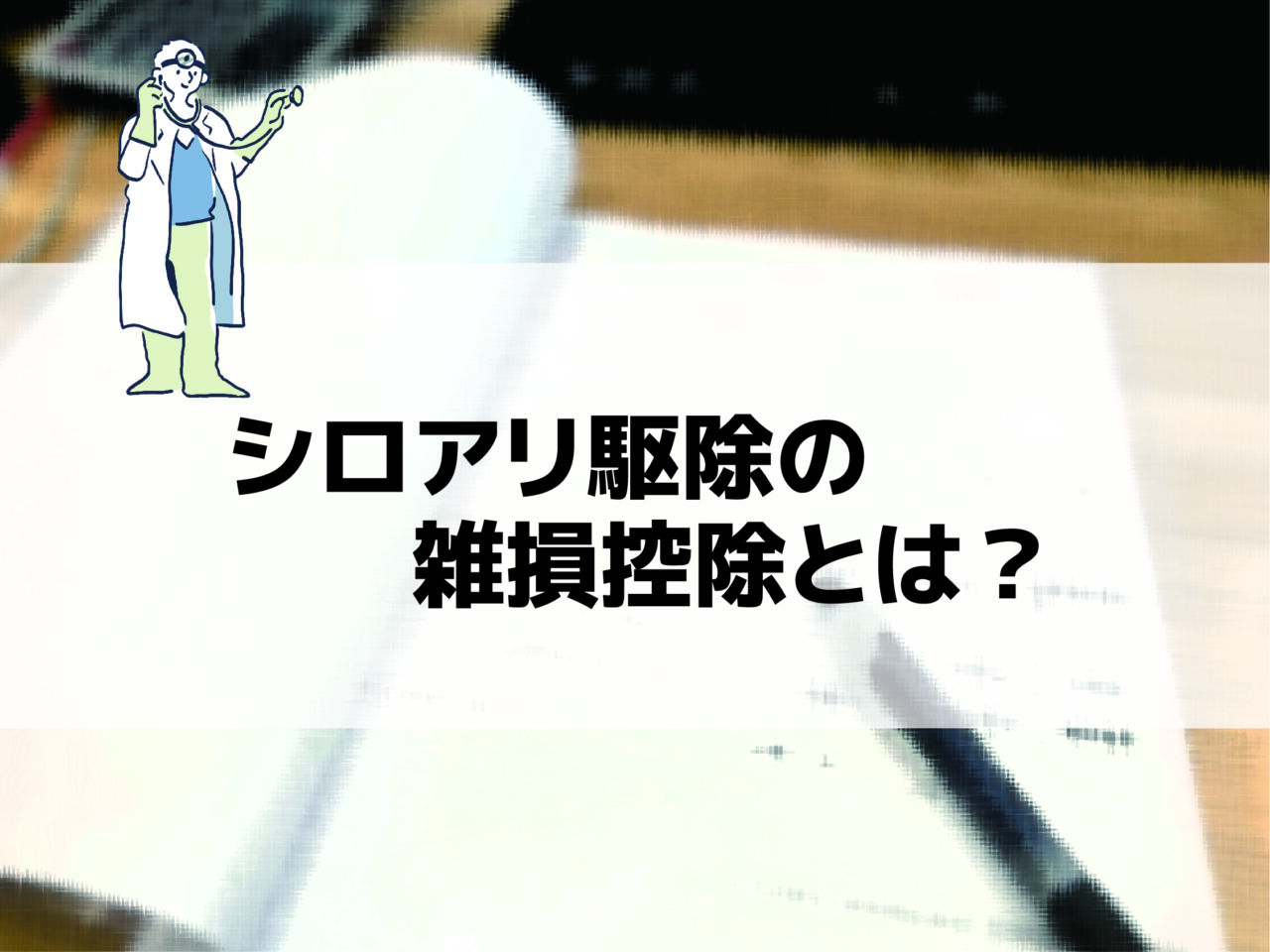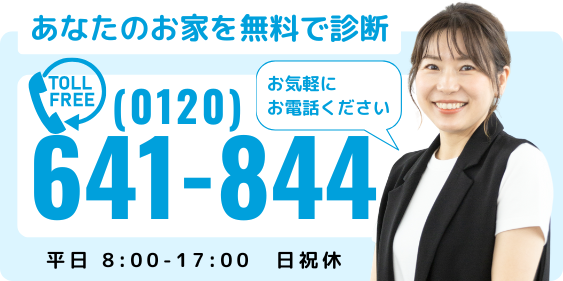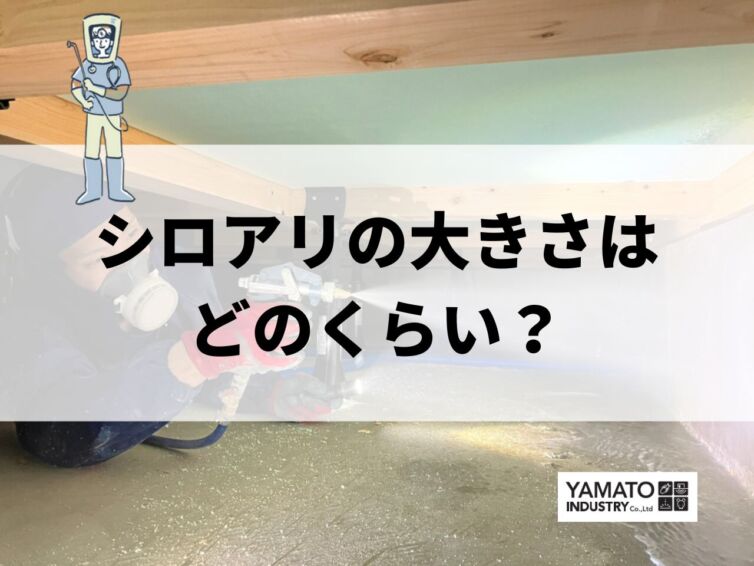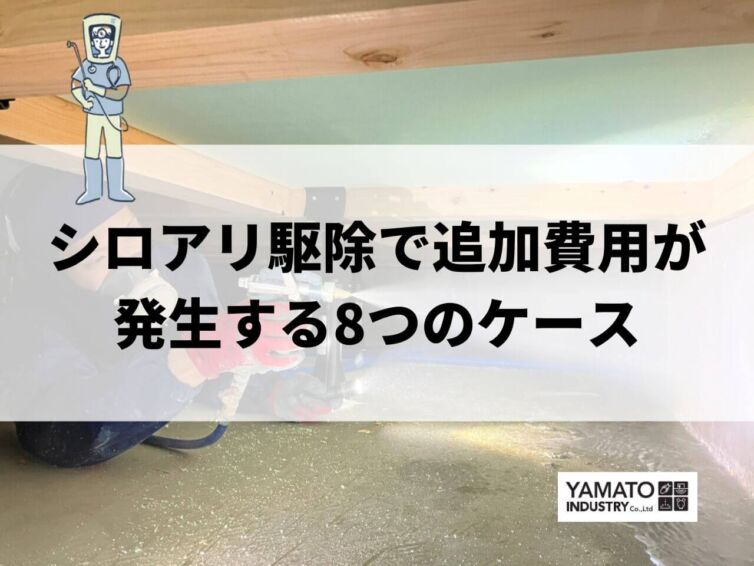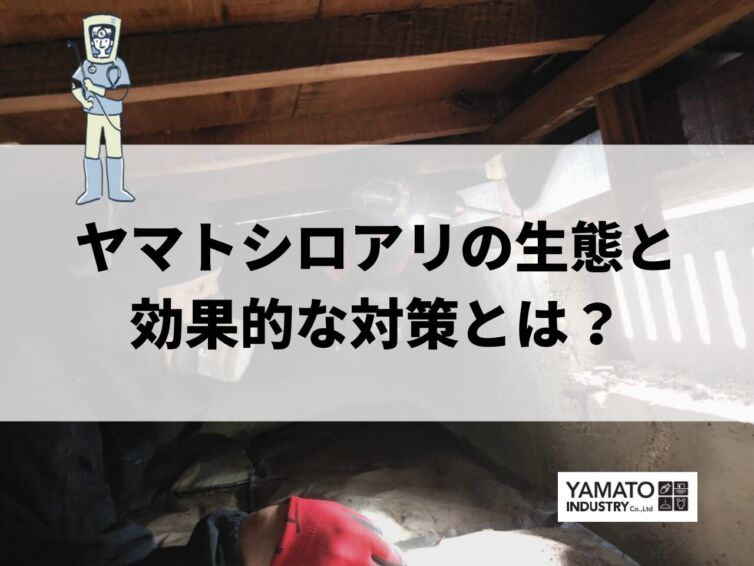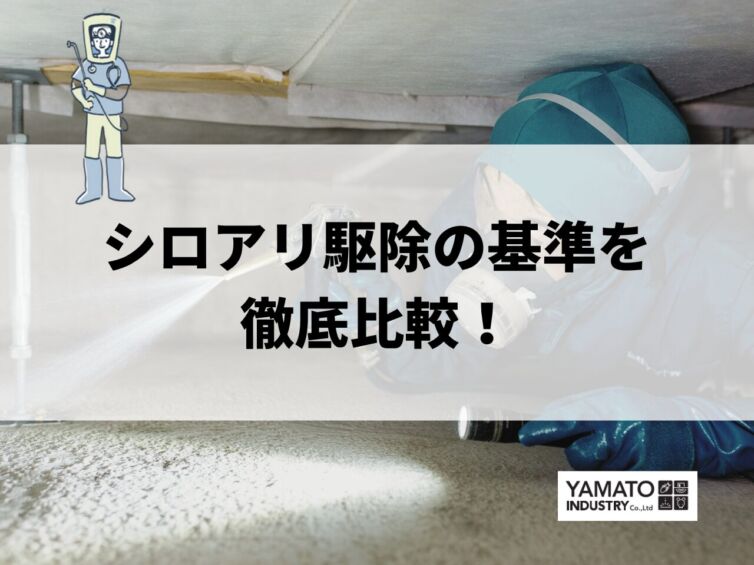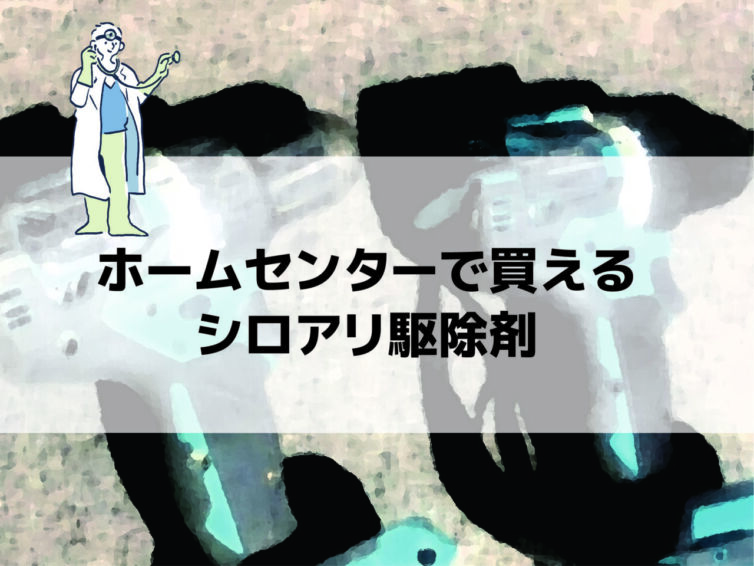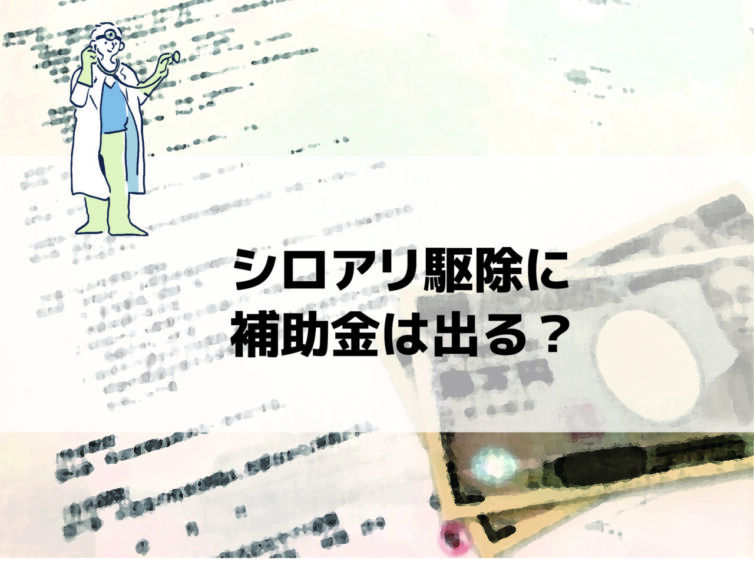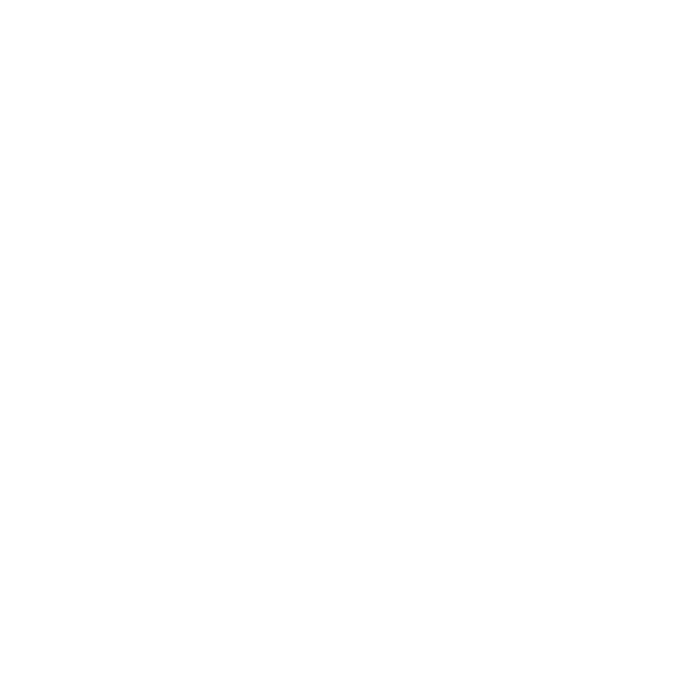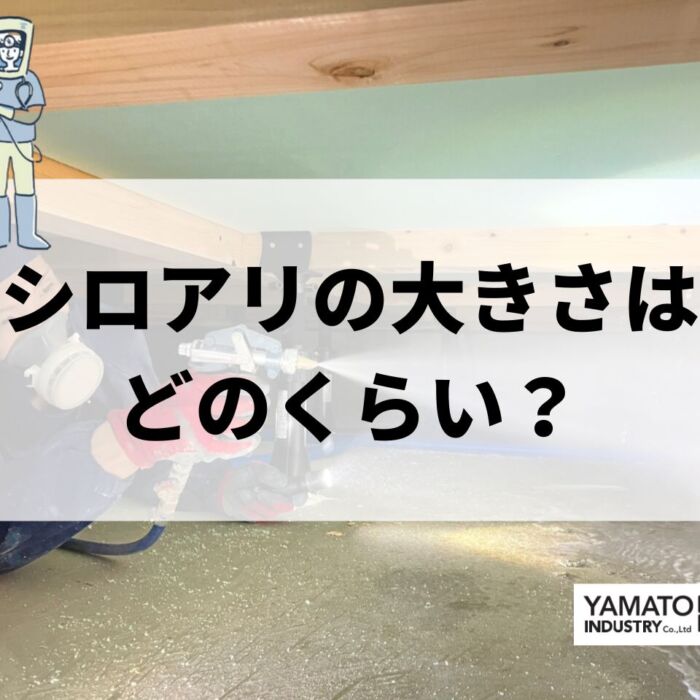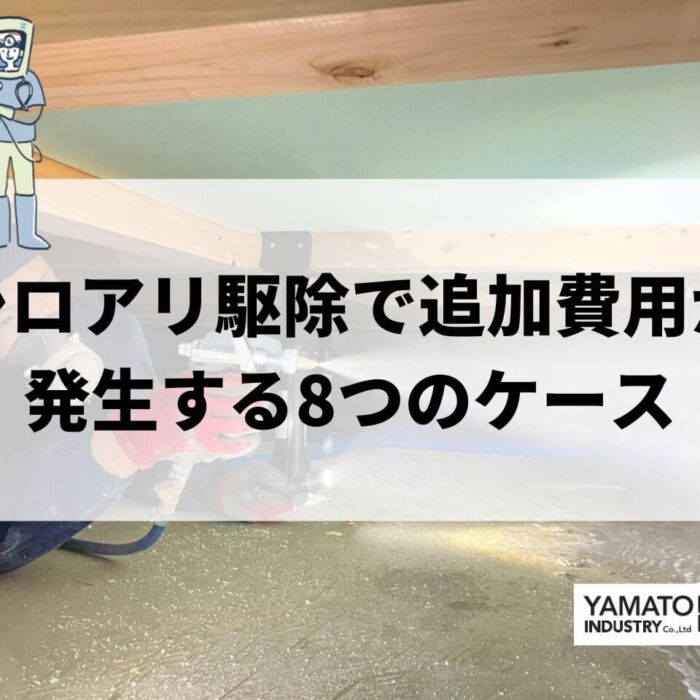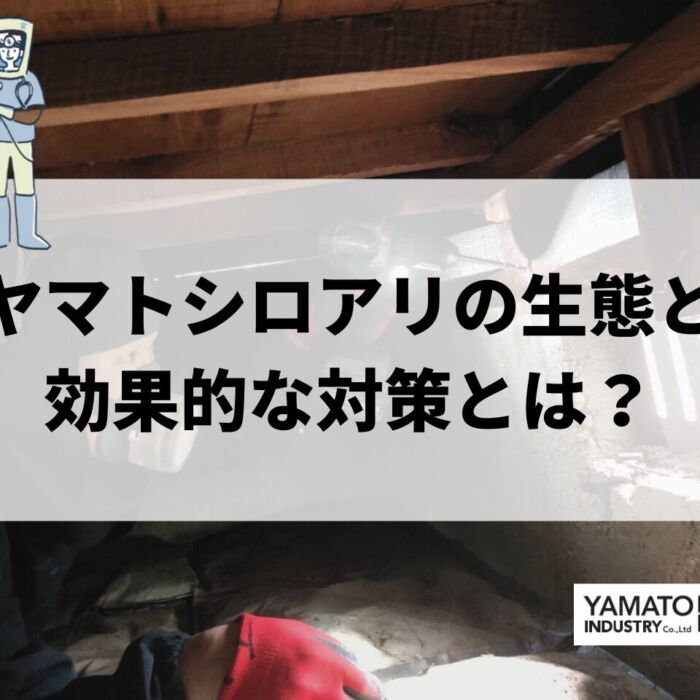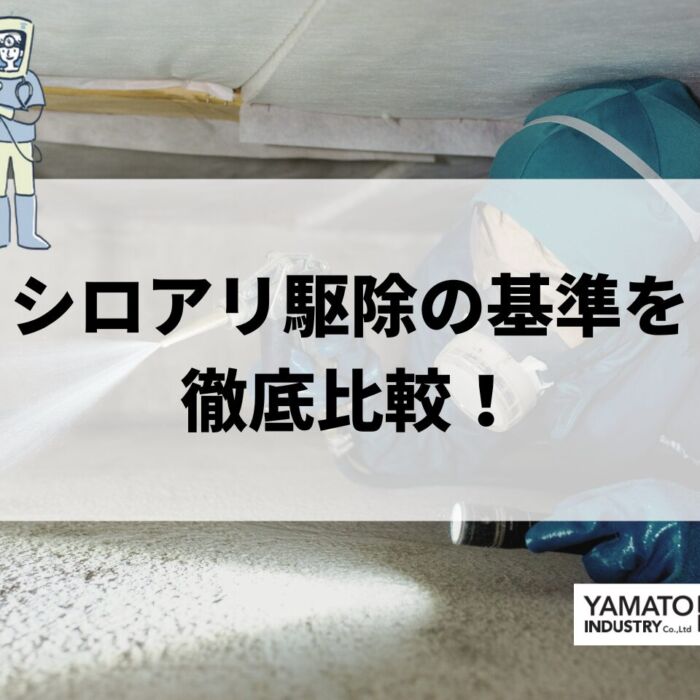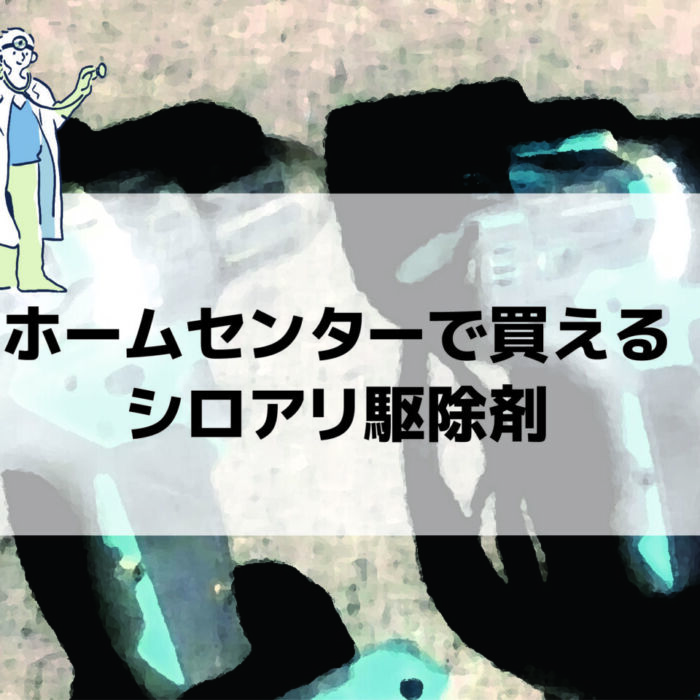「シロアリ駆除をしたけど、確定申告で雑損控除の対象になるの?」「雑損控除の条件や具体的な金額について詳しく知りたい」こうしたご質問は、当社にもよく寄せられます。自宅や大切な不動産がシロアリの被害にあったとき、多くの方が抱く疑問の1つです。
シロアリ駆除は頻繁に経験することではないため、税制上の取り扱いを知らない方がほとんどでしょう。せっかく大きな支出をしたのに、節税につながる制度があることを見逃してしまうのはもったいないですよね。
この記事では、シロアリ駆除を行った年度の確定申告において、雑損控除が適用可能か、そしてその条件と計算方法について、業界の先駆者である株式会社ヤマト産業が丁寧に解説します。
京都府宇治市に本社を置く当社は、30年に渡るシロアリ駆除の歴史を誇り、年間3,000件以上の施工実績があります。この豊富な経験と専門知識を生かし、シロアリ駆除と節税に関するあなたの疑問にお答えします。
解説するのは、私、取締役の中岡。シロアリ駆除費用は決して安くありませんので、活用できる制度があれば積極的に利用したいですよね!ぜひ、最後までお付き合いください!

下記の動画にも概要をまとめたので、ぜひご覧ください!
※税制の適用については個別のケースにより判断が異なる場合があり、また税制改正により内容が変更される可能性もありますので、詳細は最寄りの税務署または税理士にご確認ください。
【目次】
Toggle確定申告でシロアリ駆除費用は雑損控除の対象
シロアリ駆除費用は、確定申告で雑損控除の対象になります。高額な駆除費用に悩んでいる方にとって、税制上の救済措置があるのは心強いですね。
所得税法施行令に基づき、シロアリ被害による駆除費用は雑損控除として認められています。つまり、適切に申告すれば所得税の還付が期待できるということです。
なぜシロアリ駆除が控除対象になるの?
シロアリ駆除が雑損控除の対象となる根拠は、所得税法施行令第9条にあります。この条文では「害虫その他の生物による異常な災害」と定められており、シロアリ被害はまさにこの害虫による災害に該当するのです。
また、所得税法施行令第206条第1項第3号では、雑損控除の範囲を「被害の拡大や発生防止のための緊急的な措置に基づく支出」と規定しています。シロアリ被害の拡大防止や発生防止のために急遽行った駆除費用も、この緊急的な措置に含まれます。
シロアリ被害はなぜ「災害」なの?
「シロアリ被害が災害って本当?」と疑問に思う方もいるでしょう。実は、シロアリ被害が災害として扱われるのには明確な理由があります。
シロアリは地中や木材内部で活動するため、被害が表面化するまで気づきにくい特徴があります。発見した時にはすでに深刻な被害が進行していることが多く、緊急的な対応が必要になります。
このような予測不能で急激な被害拡大の性質が、税制上では「異常な災害」として認定される理由なのです。

会社の年末調整では手続きできません
重要な注意点として、雑損控除は会社の年末調整では手続きできません。会社員の方は普段、年末調整で税金の手続きが完了しますが、シロアリ駆除の雑損控除は別途自分で確定申告をする必要があります。
すでに年末調整済の場合でも、確定申告で追加の還付が見込めるので安心してください。
以上、シロアリ駆除費用が確定申告での雑損控除によって税制メリットを受けられることを解説しました。適切な申告で駆除費用の負担を軽くしましょう。
シロアリ駆除の雑損控除で適用条件&計算方法
シロアリ駆除費用の雑損控除は誰でも適用できるわけではなく、条件を満たし正しい計算方法で確定申告する必要があります。「うちの場合は対象になるの?」「いくらくらい控除されるの?」といった疑問を、具体的な条件と計算式で解決していきましょう。
雑損控除の適用条件
雑損控除の適用には、以下の条件を満たす必要があります。まずはあなたの状況がこれらに当てはまるかチェックしてみてください。
雑損控除の対象になる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方
(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。損害の原因
次のいずれかの場合に限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
※引用:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁
住宅や衣類など、生活に欠かせない資産であることが必要です。事業用の資産や別荘などは原則として対象外となります。また、貴金属や書画・骨董などで1個または1組が30万円を超えるものも「生活に通常必要でない資産」として対象外です。
また、実際にシロアリ被害が発生していることが前提です。なお、住宅が倒壊した場合の取り壊しや撤去費用も、シロアリ被害が原因であることを証明できれば控除対象になります。
雑損控除の計算方法
雑損控除の計算には2つの方法があり、金額の大きい方を選べます。どちらが得になるか、実際に計算して比較してみることが重要です。
(1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
※引用:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁
まず(1)は、差引損失額から総所得金額の10%を差し引いた金額が控除額となります。年収600万円の場合、差引損失額から60万円を引いた残額が控除対象です。
次の(2)は、住宅の取り壊しや撤去などの災害関連支出から5万円を差し引いた金額が控除額になります。この方法は、倒壊による撤去費用がある場合に有効です。
以上、シロアリ駆除における雑損控除の適用条件と計算方法を整理しました。先に条件を確認し、2つの計算方法で最も有利な方を選択して確定申告に臨みましょう。

【注意】シロアリ予防費用は雑損控除の対象外
シロアリ予防費用は、雑損控除の対象外となります。「シロアリ駆除も予防も同じでしょ?」と思われがちですが、税制上では明確に区別されているのです。
なぜ予防費用は控除されないの?
雑損控除は「切迫している被害の発生を防止するための応急措置に係る費用」が対象であり、シロアリの事前予防費用は「応急的措置に係る費用でない」ため対象外とされているのです。
予防は被害発生前の対策であり、駆除は被害発生後の緊急的な対応という違いがあります。
| 分類 | タイミング | 雑損控除 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 駆除 | 被害発生後 | ◎ 対象 | 緊急的対応 |
| 予防 | 被害発生前 | × 対象外 | 計画的管理 |
つまり、住宅メンテナンスの一環として行う予防と、被害対応として行う駆除では、税制上の取り扱いが根本的に違うということですね。
どこまでが対象?判断に迷うケース
実際の現場では、駆除と予防が同時に行われることも多く、判断に迷うケースがあります。以下のポイントで整理してみましょう。
【雑損控除の対象となるもの】
- シロアリ被害が確認された箇所の駆除作業
- 被害拡大防止のための緊急処理
- 駆除に伴って必要になった床下修繕
【雑損控除の対象とならないもの】
- 新築時に行う予防処理
- 5年ごとなど定期的な予防メンテナンス
- 被害が見つかっていない箇所への予防散布
シロアリ駆除と予防が混在している場合は、見積書で明確に分けて記録することが重要です。税務署で説明を求められた際にも、根拠となる書類があれば安心ですね。
ヤマト産業の専門的視点からのアドバイス
私たちは、お客様の大切な資産と安心を守るためにシロアリ予防をおすすめしております。
将来的なリスクを軽減できるだけでなく、被害が出てからのシロアリ駆除は高額になるからです。駆除は雑損控除が認められるとはいえ、予防で未然に防げるに越したことはありません。
予防しておけば、本来支払う必要のない費用を避けられる場合は多いです。家の資産価値を含めたトータルで見ると、予防しておいた方がお得であると私たちは考えています。
※ただし、現状ではシロアリ予防にかかる費用は雑損控除の対象外となりますので、その点はご了承ください。

シロアリ駆除の雑損控除は5年さかのぼって確定申告OK
税法における還付請求権の時効は5年間です。現在から5年以内にシロアリ駆除を行った方は、その年度にさかのぼって雑損控除の確定申告ができます。
「昨年駆除したけど申告してない…」「3年前の駆除費用も控除できるの?」といった方には朗報ですね。当時は雑損控除を知らなかった、手続きを忘れていたという場合でも、領収書などの証拠書類があれば申告できます。
申告忘れの駆除費用がないか、過去5年間を振り返ってチェックしてみてください。条件を満たしていれば、思わぬ還付金を受け取れることもあるでしょう。ただし、状況によって手続き方法が異なるので注意が必要です。
会社員なら5年以内に還付申告が可能
確定申告義務のない会社員の方は「還付申告」という手続きで雑損控除を受けられます。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出可能です。
たとえば2025年なら、2020年~2024年の駆除費用が還付申告の対象期間内になります。くれぐれも年末調整では雑損控除は適用できないため、会社員でも自分で申告する必要があります。
確定申告済みでも5年以内なら修正可能
すでに確定申告を提出済みで、後から雑損控除の必要性に気づいた場合は「更正の請求」という手続きが必要です。この更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に行えます。
ここまでをまとめると、
【未申告の場合】
- 会社員:5年以内に還付申告
- 個人事業主:期限後申告(延滞税等のペナルティあり)
【申告済みの場合】
- 会社員:法定申告期限から5年以内に更正の請求
- 個人事業主:上記に同じ
個人事業主の方は毎年確定申告を行うため、申告済みのケースがほとんどでしょう。該当するシロアリ駆除費用がある場合は、5年の期限内に更正の請求を行ってください。
まとめ:シロアリ駆除費用は雑損控除で節税しよう
高額なシロアリ駆除費用に頭を悩ませていた方も、確定申告で雑損控除という制度があることをご理解いただけたでしょうか。条件をクリアしていれば、税制上の救済を受けられ、実質的な負担軽減につながるはずです。
また、予防費用は雑損控除の対象外ですが、シロアリ再発防止のための投資は別途実施すべきです。再び被害が発生すれば、同じように高額な費用がかかってしまうからです。予防により、これ以上の被害を出さないことが大切です。
シロアリ駆除が完了した方の中には、他の箇所の状況が気になっている方も多いのではないでしょうか?
実は駆除後にこそ予防的な診断が重要になってきます。この機会に床下全体の安全性を確認しておけば、将来への不安も解消されます。
関西地域にお住まいの方でしたら、私たちヤマト産業にご相談いただけます。30年以上の実績で培った技術力により、駆除後の状況確認から今後の予防対策まで、無料診断で総合的にサポートいたします。
雑損控除で得られた節税分を、今度は安心への予防に活用してみませんか。長期的な住宅保護で、快適な暮らしを維持していただけるよう全力でお手伝いします!
※税制の適用については個別のケースにより判断が異なる場合があり、また税制改正により内容が変更される可能性もありますので、詳細は最寄りの税務署または税理士にご確認ください。